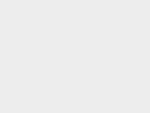
ホーム > よくあるご質問
令和6年1月に父から暦年贈与で110万円、母から相続税時精算課税制度の贈与で110万円の贈与を受けました。
暦年課税と相続時精算課税の併用は可能でしょうか、贈与税はかかりますか?
贈与者が異なるので、暦年課税と相続時精算課税は併用できます。
令和6年1月1日以降の贈与は、相続時精算課税制度に基礎控除が創設されたため、父からの贈与は「暦年贈与課税の基礎控除110万円」を、母からの贈与は「相続時精算課税の基礎控除110万円」を適用できます。
それぞれ異なる課税方式を選択しているため、贈与合計額220万円は贈与税の課税対象から控除されるので、贈与税はかかりません。
※贈与税の申告書の提出はありませんが、相続時精算課税を選択する場合は令和7年2月1日~3月17日までに「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
※相続時精算課税を選択した場合、その後、同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ変更することはできません。
(令和6年12月20日時点の法令等に基づいて記載しております)
会社は債務超過の状態であり多額の役員借入金を返済できません。社長が債権を放棄することはできますか。
債務超過の会社が役員借入金を返済できない場合、社長が債権を放棄することは可能です。ただし、正式な手続きを踏む必要があります。社長と会社の間で債権放棄に関する書面を作成し、放棄の内容、金額、日付などを明記します。その後、会社は債務免除益を計上する必要があり、繰越欠損金があれば法人税が課税されない場合もあります。
法人がスポーツ少年団、部活などに協賛金を支払った場合、経費として計上できますか?
得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対するものは、交際費に該当します。
事業に関係のない相手の場合で、宣伝効果を目的として協賛金を支払う場合は宣伝広告費になります。この場合、不特定多数の人に向けて宣伝効果があることが前提となります。
宣伝効果もなく、事業に関係のない相手の場合は、寄付金となります。寄付金は、一定の範囲内での損金算入となります。
協賛金の目的によって判断する必要があります。いずれにしても帳簿にしっかり内容を記載し、証憑書類を保存しておきましょう。
接待ゴルフ費用で、経費として認められるものと認められないものを教えてください。
ゴルフにかかる費用で、経費として認められるかどうかは、その費用が「会社の業務に関係しているかどうか」がポイントになります。経費にできるのは、得意先や業者とのゴルフのプレー代、ゴルフコンペの景品代、法人がゴルフ場の入会金等を支払、資産として計上している場合の年会費、ゴルフ場への往復交通費、取引先との飲食代、コンペ開催時の景品代などです。 一方、経費にできないものは、従業員同士でのプレー費用や練習費用、ゴルフ用品の購入費用、ゴルフ保険の 費用などです。ただし、従業員だけで行ったゴルフプレーやコンペは福利厚生費として計上できる場合もあります。
インボイスの登録をしたのですが税負担が多く登録を取消したいと思っています。どのような手続きが必要でしょうか。
インボイス制度の適格請求発行事業者の登録を取消すには、以下の手続きが必要です。
これにより、次の課税期間(提出した日の属する課税期間の翌課税期間)から登録が取り消されます。
参考文献:国税庁ホームページ
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf)
孫のために、孫の名義で預金していますが、私が死んだらこの預金は自動的に孫のものになるのでしょうか?孫には預金の存在を伝えていません。
ふるさと納税の仕組みとメリットについて教えて下さい。
ふるさと納税は自身の選んだ自治体に寄附を行うことで、所得税や住民税の控除を受けられる仕組みです。控除を受けられる上限は納税額によっても異なりますが、寄附額から2,000円を引いた金額になります。例えば35,000円のふるさと納税を行った場合は寄附額から2,000円を引いた33,000円が所得税や翌年の住民税から控除されます。
※ふるさと納税のメリット
寄附のお礼として、その地域の特産品や商品を受け取ることができます。例えば、地元の農産物、海産物、工芸品、旅行券など、地域ごとに魅力的な返礼品が提供されており、実質的な自己負担額2,000円で多くの品物が手に入ります。
2.地域貢献ができる:
自分が応援したい地域に寄附をすることで、地方自治体の財政支援や地域活性化に貢献できます。災害に見舞われた地域など、特定の支援が必要な場所を直接サポートできます。
3.自治体を自由に選べる:
日本全国の自治体が対象となるため、どの自治体に寄附をするか自由に選べます。地元以外にも、旅行先や興味のある地域、特定の政策や活動に力を入れている自治体を選べる点が大きな魅力です。
確定申告を必要とせず寄附の手続きが完了する「ワンストップ特例制度」を利用すれば、5つの自治体まで寄附しても簡単に控除を受けることができます。これにより、忙しい人でも手軽にふるさと納税を活用できるメリットがあります。
法人で車両を取得するのですが、今期は利益が出るのでなるべく経費を多く計上したいと考えています。
購入と5年リースだとどちらが減価償却費を多く計上できますか?
購入の方が今期に多く減価償却費を計上できます。
購入した車両の法定償却方法は定率法が適用され、リース資産の場合はリース期間定額法が適用されます。
例)300万円の普通車両、法定耐用年数6年、リース期間5年
今期の減価償却費は購入の場合999,000円、リースの場合600,000円となり購入した方が減価償却費が多く計上されます。(期中取得の場合は月数按分が必要です)
【相続税】
契約者、被保険者、受取人=相続人(長男)
保険料負担者=被相続人(亡くなった人=父)の場合、この保険は相続財産となりますか?
保険料は一時払いで、父の預金口座から支払っていました。
この保険契約は「名義保険」と判断され、相続開始時点の解約返戻金相当額で相続財産となる可能性があります。書類上は被相続人の氏名が出てこないため、相続税には関係ないと思われがちですが、保険料負担者が被相続人である場合は注意が必要です。
特別償却と税額控除のどちらを選択した方が税負担を軽減できますか?
特別償却とは普通償却の他に償却費の上乗せを認める制度です。
特別償却は課税を以後の事業年度に繰り越せるので、購入初年度は特別償却を選択した方が税負担を軽減できます。
税額控除は免税ですので、償却期間が終了するまでを通して考えると税額控除の方が税負担を軽減できます。
どちらを選択するか判断するためのポイントは、償却期間の合計の法人税額をトータルで減少させたい時は免税である税額控除を選択、資金繰りの関係で、とにかくその期の法人税額を軽減したい時は特別償却を選択すると有利です。
新たに機械(バックホー)を購入したいが設備投資による税務上の優遇措置はないですか?
中小企業などが新品の機械及び装置等を取得し、事業の用に供した場合には、特別償却又は税額控除の特例を受けることができます。
退職金準備を考えています。まず従業員の退職金準備から始めようと思いますが、どのような方法がありますか?
一般的に利用されているのは次の方法があります。
◎中小企業退職金共済を利用
~中退共制度の特色~
☆ 掛金の一部を国が助成します。
☆ パートタイマーの方も加入できます。
☆ 掛金は税法上、全額非課税になります。
☆ 過去の勤務期間通算や企業間を転職した場合に通算ができます。
☆ 掛金は預金口座から振替えます。退職金は直接退職者に支払いますので、管理が簡単です。
加入申込書はお近くの金融機関又は委託事業団体の窓口にあります。
◎中小企業退職金共済を利用
~中退共制度の特色~
☆ この制度は、従業員の退職金を損金あるいは必要経費として計画的に準備できます。
☆ 特定退職金共済は、商工会議所が「特定退職金共済団体」として国の認可を得て実施しています。
☆ 掛金は、月額1,000円から30,000円まで1,000円刻みで選べます。
☆ 掛金は全額損金又は必要経費として認められます。
お近くの商工会議所にお問い合わせ下さい。